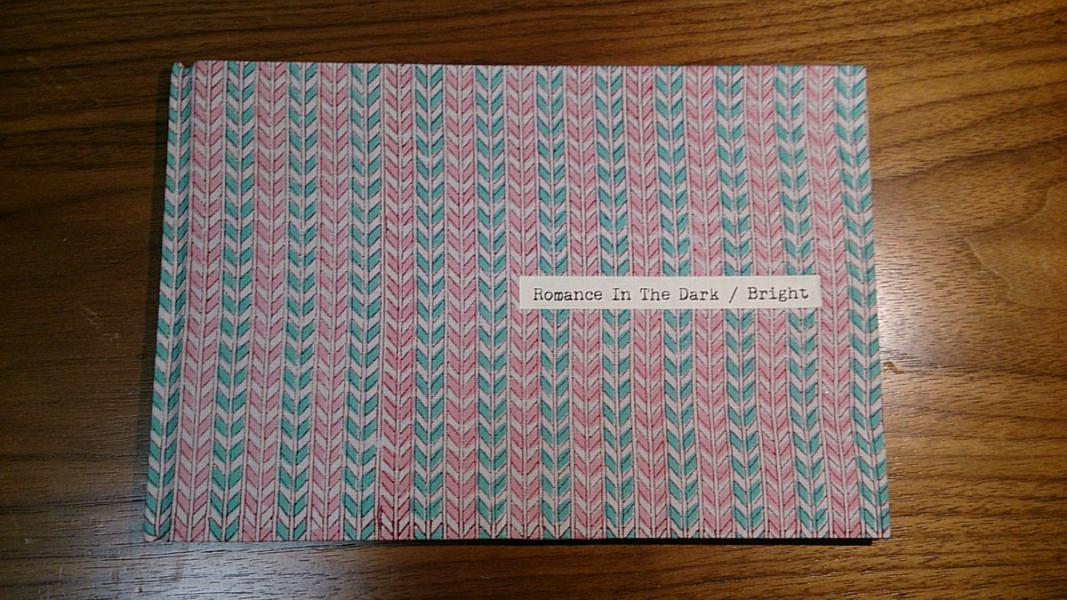|
「……そう。あのひとから帰って来いって手紙が来たの」
久しぶりに母の家を訪ねる。
寄宿学校近くのバス停から都市間(インターシティ)バスに乗って、あらかじめ運転手に伝えておいた、農地以外になにもない場所で止めてもらう。羊や牛がまばらに草を食む牧草地のなかを、てくてくと四十分ほど歩くと、母の小さな家があった。昔ながらの農家を少々改装した、白壁の切り妻屋根の家。そばに型の古いシトロエンと、ささやかな野菜畑、盛りを迎え始めた野ばらとあじさいの茂みがある。
その日は体調がよかったらしく、彼女は居間のテーブルで黄ばんだフランドル派の画集をめくっていた。
家政婦兼看護師のマーレイは、部屋の隅でふたり分の紅茶を用意してくれている。
わたしは母と同じテーブルの椅子に座り、青く塗られた窓枠のなかに見えるこの国らしい景色を眺めながら、ぼそぼそと言った。
「中高等学校(セカンダリ・スクール)に入ってから、全然帰ってなかったから。顔を見たいって。……さすがに、三年も顔を見ていないと、心配だからって。正直、行きたくない」
「どうして?」
何の感情もこもっていないように見える、母の灰色の目に見つめられる。
わずかな怒りと悲しさが胸に生じたのを感じた。
「……あのひとに、会いたくない」
母はわずかに口元に笑みを乗せた。
「仕方ないでしょう。父親なんだから」
「会いたいなんて、入学してから一回も思ったことない。あのひとを、もう父親だなんて……思えない」
母の笑みは困ったような形に変わる。
「……そんなこと言わないで。悲しくなるわ」
――悲しくなる。
母は感情の振れ幅が激しくなる病を患っていた。もう、五年近くになる。気分が落ち込んだときはベッドから出られず、食事や睡眠もままならなくなる。普段でも、長時間文章を読んだり作業をしたりするのは困難で、時折散歩をしたり、村に出て買い物をするのが精一杯だ。おおきな音やまぶしい光に敏感で、トラックの走る幹線道路やおおきな街に行くこともできない。
母を悲しませるためにここに来たのではなかった。
「ごめんなさい。でも、あの島は嫌いじゃないんだ。シャノンにも会いたいし。リアム兄さんはスペインに行っちゃってるけど。だから……」差し出された紅茶を一口飲んだ。「夏休みのあいだ、行ってこようと思う」
|