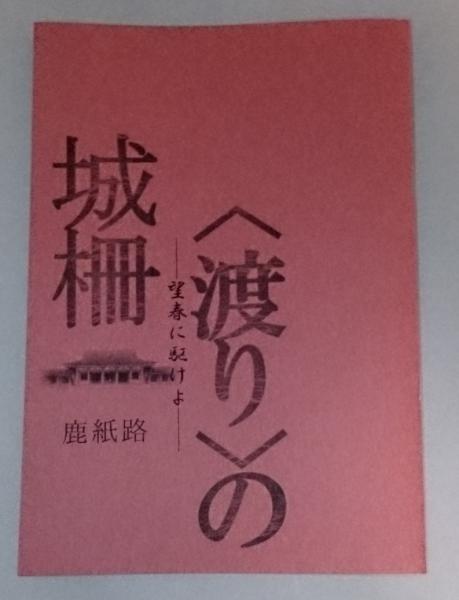|
「見よ、春野。望春である」
白い息を吐きながら、父は熱い手で春野のちいさな手を引いた。
「ぼう、しゅん?」
稚い少女の円まどかな目に、北辺の早春が映る。
灰色の厚い雲を、一筋、明るい光が割り、雪と黒々とした裸の木々を照らす。父の指先が示すのは、その木々のうちのひとつ――……しかし、その木末こぬれには目に沁みるようなあでやかな紫の花が付いている。しなやかな美女の、握りしめたこぶしのようなつぼみは黒く点々と木に見えるが、咲えみひらいているのはそのひとつだけだ。
長細い花弁の紫の花――
「木蘭を、大陸ではそう呼ぶ」
「きれい」
「うむ。春野と、同じ字を持つ花である」
父は、目尻の皺に目をうずめるように微笑み、寒さで赤くなった春野の頬をさすった。
「父上、」
父が急に自分に触れたので、春野は驚いた。身をこわばらせる間もなく、父は軽々と自分を抱き上げた。
「届くか?」
ひとつだけひらいた花に、春野は手を伸ばす。
「いいえ、父上」
木蘭の枝は遠く、春野は手を空ぶらせた。
「だろうな」
からからと、父は笑った。そして、髭に覆われた頬を春野に寄せる。
「父上、痛いです」
両手で父を押しやろうとしても、彼は一向に意に介さない。
「いまに、届くようになる」
彼は久しぶりの日差しに目を細める。
遠辺国守風声千弓の娘、春野は八歳で、その年、父の任地に来て初めての春を迎えた。
都と異なり、雲が丸ごと落ちてきたように降り落ちる雪も、きびしい吹雪も、少女にとってはこころ躍ることだった。同じ年頃の子どもたちの輪に飛び込み、彼らのする雪遊びをして、雪まみれになって風邪を引いたこともある。
川が凍り付き、歩いて対岸に渡れることも、つららが軒に連なることも、春野は全身で楽しんだ。どこまで駆けても、そこには雪があった。白と黒の世界で、彼女は頬を赤くして転げまわった。
都で一緒に暮らした母は死んでしまった。
だから、彼女は父のもとに来て、父のようになる術を学ぼうと思った。夷似枝と呼ばれる自分たちとは異なる習俗を持つひとびとと、百姓が共に生き、田を耕し、実りを得る、この広い広い雪原で。
春野は金色の光を浴びて、もういちど手を伸ばした。
|