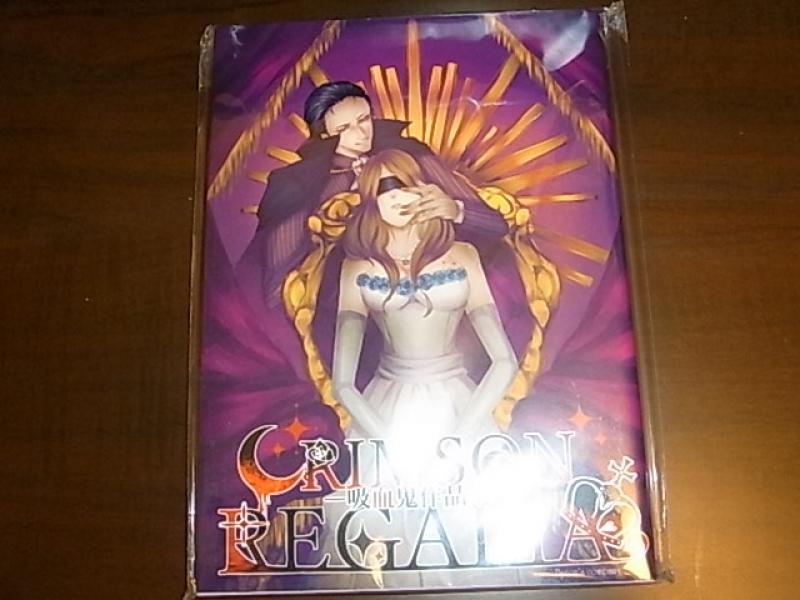|
「頼まれていたものは用意したわ」
繻子織りの仕切り幕の向こうで、しどけなく長椅子に腰掛ける娘が、金色の鍵をひとつ差し出しながら呟いた。
歳の頃は二十歳を越えぬあたり。
月光冴え渡る夜の色をした瞳、絹の如き白い肌。
漆黒の絹織りの扇を弄ぶほっそりとした指先もまた透けるような白さで、血の気がない。
ところどころに混じる金髪が、豊かな巻き毛を飾る金細工のようにも見える濃い茶の髪。
胸元にいくつも真珠を縫い止めた深緑のドレスの腰を細く締め上げて科を作るさまは、歳の頃に見合って控えめではあったが、ぞくりとするほど艶めかしい。
人形のように美しい娘であった。
仕切り幕を持ち上げて、『個室』に入ってきた男を、不躾にも思える、あけすけな興味の宿る眼差しで眺め遣り、手に持っていたグラスの飲み物をひとくち、口に含む。
年頃の、身分卑しからぬ娘にしては物怖じせぬ振る舞いである。
入ってきたのは、店主に『公』と呼ばれていた男である。
猛禽に似た鋭い視線で娘を捉え、ふと溜息を吐いた。
「額は」
「英国通貨で二万ポンド。これ以上をお望みなら、もうしばらく時間が欲しいわね」
「いや、当面はそれで充分であろうよ」
男は娘から鍵を受け取り、娘の右手に腰を下ろした。
「暗証番号は『一四七六一二一九』貴方にとっては意味のある数字でなくて?」
鍵には墺太利=匈牙利銀行の貸金庫の刻印があった。
男は、娘の言葉には応えなかった。ただ、わずかに同意とも取れる微笑を唇の端に浮かべたのみ。
「貴方が領土を離れるなんて、いつ以来のことかしらね?」
上品な微笑を口の端に、娘はもうひとくち、グラスの飲み物を口に含む。
珈琲に似て異なる、独特の苦みのある豊かな香りがあたりに漂った。
「みな、そう言うが、我らにとって歳月になんの意味がある?」
いくばくか辟易したように唇を歪め、男は答えた。
(「Hexennacht」より抜粋)
|