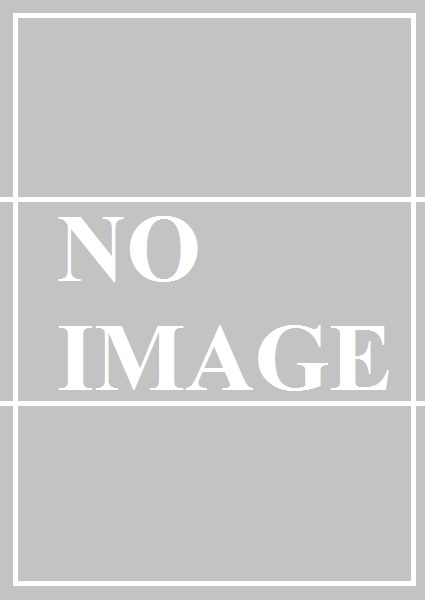|
(『スメルス・ライク・レッド』より)
あーあ、今日も吐きやがった。嘔吐物との戦いは駅の清掃員の日常である。原型をもはや留めていない食物。溶媒になるのは胃液。そこにまじった分解されていない酒が放つアルコールの匂い。特に休日前の清掃は地獄の沙汰だ。
毎日毎日汚物との戦い。働く場所がないので仕方なくやっている。最初はねじまって落ちてしまいそうだった鼻も、耐性がついたとはいえ丸一日汚物と向き合って家に帰るころにはバカになっていた。まず食べ物の味がわからない。俺の嗅覚が敏感すぎるというのもあるかもしれないが、何を食べても味がしない。でも食べないよりはましだ。そう言い聞かせながら、何年も毎日、駅の浄化に努めている。
そんな底辺労働者の俺にも楽しみはある。女子トイレの掃除だ。
女子トイレの清掃は気まずさとの戦いでもある。このご時世、清掃の折りには「男性清掃員が清掃しています。ご了承ください。」といった立て札をわざわざかけなくてはいけない。それを見て立ち去っていく女性もたまにいる。
別に俺たちだって、好きで掃除をしているわけじゃない。やることがなかったからこの仕事についているだけだし、女子トイレの清掃だって、「やれ」って言われたからやっているだけだ。
女子トイレの清掃は楽しみの一つだとはいったが、別に排尿音を聞くのが楽しみというわけでもない。俺は別に女子の排尿行為に興奮するわけではない。ただの水が流れる音にしか聞こえない。これで興奮する男の気持ちは全くわからない。自分たちだって排尿をする。その場所が、構造が違うだけだ。床にこぼれた尿はそれなりの悪臭を放つし、便だって男のそれと変わらない。むしろ見たくない部類だろう。それらを俺はせっせと除去し、便器と床を磨き上げ、トイレットペーパーを三角に折り畳む。
そのあとだ。俺の楽しみは。女子トイレの個室にたたずむ汚物入れ。その中だ。さびた小さな鉄製のゴミ箱をあけると、そこには大量の使用済み紙ナプキンが詰め込まれている。自然と鼻腔がひろがっていくのがわかる。
|