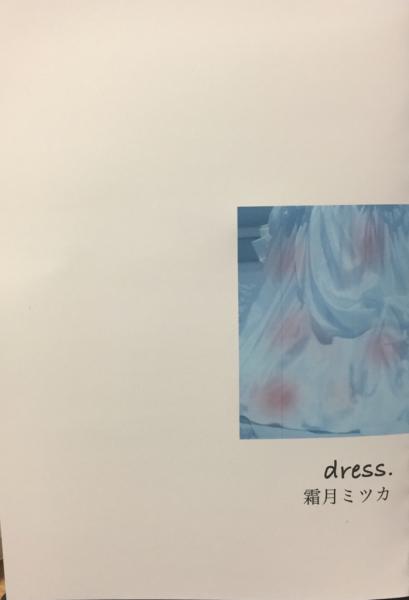|
玄関でパパに抱きしめられるママの姿を見てしまった日は、それだけで最悪の一日だ。パパにひっつくママの後ろ姿はか弱い少女で、普段のママとは別人だった。
パパはママを抱きしめる腕をなかなか緩めようとせずママの服に皺をつくっていた。
何より憎たらしいのが、その様子を娘が観察しているなんてまったく意識せず、熱く抱擁しつづけていることだった。
ひとしきり、お互いの感触を確認したあと、パパが腕を緩めてママに一度軽くキスをする。これがこの恍惚な時間の終わりの合図だ。
わたしは息を潜めてすぐに逃げられるように準備をする。
「行ってきます」
パパが世界中でママにしか聞き取れないくらいの声量でそう言う。ママはいつもパパに「行ってらっしゃい」と言っていたのか、わたしには聞き取れなかった。
わたしのママはいつも完璧だった。
いつも笑顔で、怒っているところを見たことがない。わたしたちきょうだいが悪いことをしていたら注意はするけれど、怒りを出すことなく、いつも優しく何が悪いのか教えてくれた。家はいつも埃ひとつなく、どこもかしこも完璧に磨かれていて、料理も上手だったし、栄養のバランスが考えられていた。そして、何より美しかった。公園や、学校の授業参観、スーパーで出会うひと、皆ママより美しいひとなどいなかった。
自分で言うのもなんだけど、我が家は街で一番大きな家だった。そこに、基本的にママと五人のきょうだいで暮らしていた。
パパは芸能人をしているらしい。
家のテレビはいつも黒い鏡みたいで一度もパパのことを映すことがなかった。リモコンはいつもママが持っていて、ママが許可しない番組は見ることができなかったけれど、友だちの家みたいにNHK以外は見せないみたいな縛りはなかった。ただ、頼んでも見せてくれない番組はあった。そういうとき、ママは困った顔をして「どうしても」ということばに逃げた。パパが出てるから見せたくなかったのはわかるけれどどうしてあんなに頑なに見せようとしなかったのかはわからない。
|