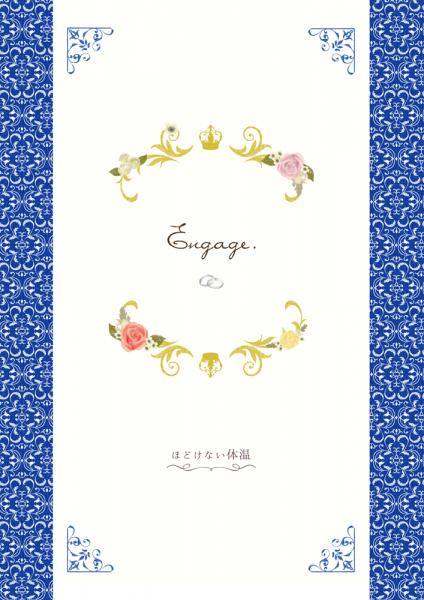|
「へっへー」
ぴかぴかに光る真新しい指輪をはめた左の掌を得意げに空へとかざしながら、もう何度目なのかわからない感嘆のため息を吐き出す。
ふたりで赴いたジュエリーショップで注文した指輪にはちゃんと名前の刻印も入れてもらって、受け取りもまた、ふたり揃って赴いた。
指輪の交換だなんてものは、気恥ずかしくて遠慮させてはもらったけれど、いつもよりも心持ちめかしこんで出かけた帰り道、手の甲をゆるくぶつけあうその度、かちりと冷たい感触があたること。その度にどこか照れたようにぎこちなく笑いかけてくれたこと――笑ってしまうほどの些細なそんな出来事ひとつひとつに心を温められたことを思い、ふつふつとわき上がるいとおしさに身をゆだねるように、やわらかに瞼を細める。
「会社に着けてくとちょっとあれだよね。周といる時は付けてるってのでいい? あと、休みの日ね」
「おう」
いつもどおりのどこかなげやりな――それでも、誇らしさを隠せない口ぶりを前に、おだやかなぬくもりはこみ上がるばかりだ。
法的な婚姻が認められているわけでもなければ、洗いざらい打ち明けるつもりもない。形だけの何の効力もないおまじないめいた物に過ぎないのだとしても、やっぱりこうして目に見えた『証』があるのはうれしい。
そうは言っても、学生ならともかく、いい大人がこれみよがしに浮かれた姿を見せびらかすわけにもいかないし――『大人』ってこんな時、めっぽう不便だ。
ほんの一匙ばかりの気落ちを、それでも気づかれないようにと振り払うそのうち、ふいにうってつけの機会が近々あったことを思い出す。
ああ、そういえば。
まだ見慣れないぴかぴかの銀の輪の上をゆっくりと指でさすりながら、おもむろに告げる言葉はこうだ。
「そういやさぁ。これ、着けてくのにぴったりなとこがあって」
|