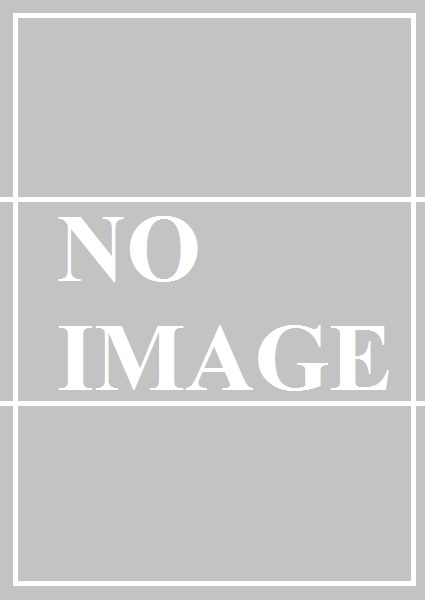|
風が吹いている。頬を撫でるのは明日香風。随行の女官たちの領巾がはためいている。遥かに下を見おろせば、民びとの住まいから炊の煙がのぼり、干した白い布が揺れていた。
「うつくしい景色ね、この新益の京は。氷高の目には、何が見えて?」
風が言葉を運んでくる。娘と、その祖母のやりとりを。
丘を飛んでいるのは、鷗だろうか。香具山で国見をした古い世の天皇の歌が目に浮かぶようだ。「大和には 群山あれど とりよろふ 天の香具山 登り立ち 国見をすれば 国原は 煙立ち立つ 海原は かまめ立ち立つ うまし国ぞ あきづ島 大和の国は」と歌われた、あの光景がそのままに。
「民びとが、その暮らしが見えますわ。お祖母さま」
「その通りよ、煮炊きの煙も干された衣も平らかな暮らしそのもの。天の香具山にひるがえっている白い衣のようにも見えなくて?」
国見の丘に立つ娘は、目を見開いて新しい京を寿ぐ祖母を見つめている。薄紫の裳を着けた娘は十代の半ば頃。結い上げた髪は瑞々しく、まだ初々しい少女の面影を残している。
新しい藤原の京に移ってまだ三月も経っていない。京はまだ造りかけで、民草の活気には程遠い状態だった。
それでも。孫娘に語る祖母には、見えているのだ……この新しい京に溢れんばかりの人が行き交い、賑やかに活気あふれる日を。
女帝は高らかに謳いあげる。丘に山に新しい京の隅々まで行き渡るような国誉めの言葉を。
「春過ぎて夏きたるらし白たへの衣ほしたり天の香具山」
風が吹いている。頬を撫でるのは……
「違うわ。ここは平城。明日香ではない」
重かった瞼をあげながら呟くと、心配そうに覗き込む娘の姿が目に入った。
「ああ、氷高。来ていたの。夢を見ていたわ、ずっと昔の、藤原の新益京にいた頃の夢を」
安心したように氷高は頷き、自分の後ろを指し示した。誰かがいるようだが影になっていてよく見えない。
「母上、檜隈が見舞いに来てくれましたの。覚えていらっしゃるかしら?従姉妹の檜隈のことを」
檜隈……ぼんやりとした頭でそれは誰だっただろうと考え、姉の夫の娘の名だったと思い出す。そう、あの日あの国見のときにも来ていたわ。檜隈女王も。
「分かるわ、檜隈……高市の義兄上の一の姫」
口に出して言うと、国見の日の古い記憶が一気によみがえってくる。
|