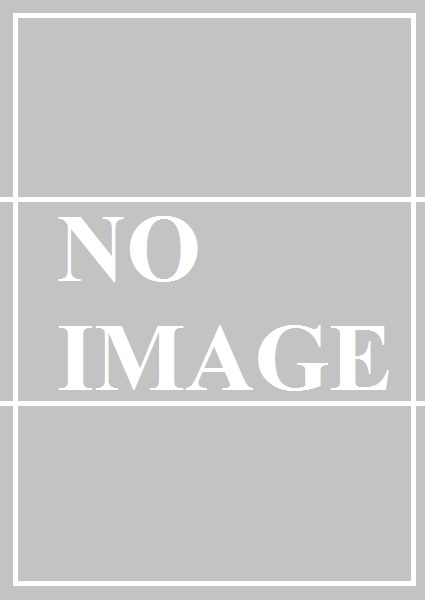|
診断書を社長に出した時、社長は相変わらず渋い顔をしていた。
「今まで残業していたんだから、これからだってできないことはないでしょう? 月何時間くらいなら残業できる?」
「えっ……」
香純は短く迷って、答えた。
「二十時間です」
「たった二十時間の残業で、何ができるっていうの? 森本君や上原君は、二百時間残業してるんだよ」
森本君や上原君は、働き盛りの二十代じゃないか。
香純が言葉を返せなくて困っていると。
「早川君」
小野塚主任が、ずかずかと社長室に入ってきた。
どうして女性の香純に、「君」つけるんだろう。香純はいつものように思った。この主任はすぐ怒鳴るので、好きになれない。
「早川君は、この会社が男ばっかりだってわかってて入社しだんだろ。だから、女だからって甘えられると困るんだよ」
香純は立ち上がった。
「別に男だからとか女だからとかいう問題じゃないんです。私は病気だと診断されたんです」
「でも、全然元気そうじゃない」
香純は、どういえばこの人にわかってもらえるか考えていた。
小野塚主任はなおも言いつのる。
「みんな文句言わないで残業してるんだから、早川君もそうしてくれないかな」
「ですからそれはできません。今までだって何度も体壊してきました」
「それは、たるんでるからだ!」
小野塚主任は怒鳴った。
その言いぐさに、香純は切れた。
そして、言ってしまった。
「怒鳴れば何でも言うこと聞くと思って。結局は私が女だから馬鹿にしてるんじゃないですか」
「いい加減にしろ!」
小野塚主任は右手を振り上げ、香純の頬を叩いた。
「――!」
香純は、ぶたれた頬を押さえた。
どうして私が殴られるの?
病気だと殴られるの?
「……殴りましたね」
香純は、低い声で言った。
「暴力をふるいましたね」
「小野塚君、やりすぎだよ」
背後から社長が声をかけるが、小野塚主任が何か言う前に、香純は叫んでいた。
「こんな会社、辞めます!」
香純は社長室を出ると、誰にともなく言った。
「私、今日で辞めます。荷物は改めて取りに来ます。お世話になりました」
唖然として見守る同僚たちを残して、香純はハンドバッグ一つ持つと、事務所を出ていった。
|