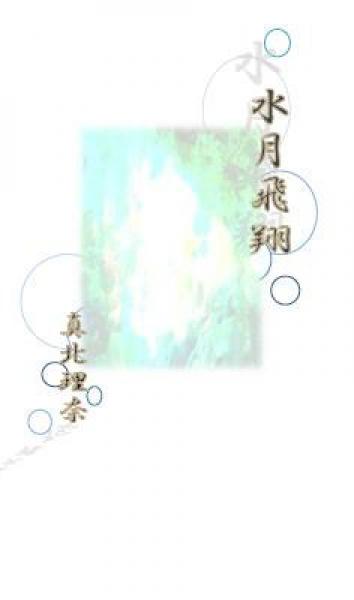|
ゆるりと、何かが食い込むような感じがして、薄れゆく意識の中で、ああ、もうだめなんだなと思った。
小さな魚だった。名前は知らないけど。
小さな魚ゆえに、食べられるのは必然。そうでなくてはほかの生物は生きていけないんだ。
それが、生きるということは、生まれた時から知っていた。本能的に組み込まれていたのかもしれない。
冒頭文P.3
自身の怪しい思惑は表に出さないよう勤め、仮面として貼り付けた。いわゆる『優しさ』と呼べる微笑を彼女に向けてみた。
すると、どうだろう。
「ありがとう」なんて言って笑ってくれたではないか。
彼女にとっては見ず知らずの自分に向かって。
どれほど嬉しいことか、きっと彼女は知らないのだろう。
──知らないままでいて。
それは、祈りにも近い、最後の砦のようなものだった。
|