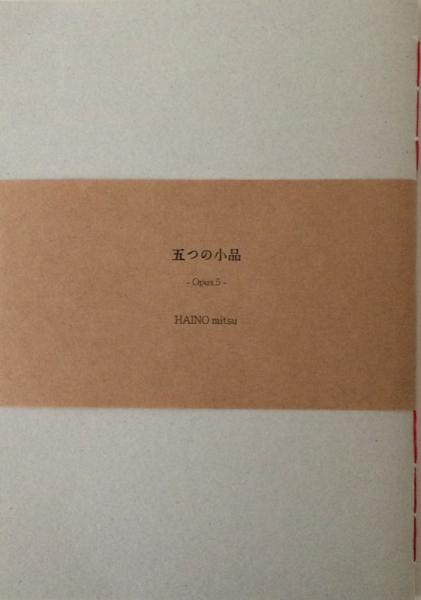|
最後の手持ち花火の灯が、滑らかな曲線描く彼女の頬を照らし出す。紅に淡く色付いた白磁は、春の夜に匂い立つ沈丁花を思わせた。耳元で密やかにさざめくような、深く、奥行きを感じさせる香り。闇に目隠しされていても、何処かで確かに咲いていると感じられる其れ。
穏やかに風の渡る川縁でふたりで花火を始めてから、随分と時間が経っていた。頭上の望月は既に西に傾きつつある。
「手持ち花火なんていつ振りだったのかしら」
薬筒の先から迸る鮮やかな火花へと眼差しをじっと注ぎながら、彼女が呟く。川のせせらぎの傍にあっても、彼女の声は普段と変わらぬ響きを持ち、何よりも優先されて私の耳に届く。
「花火が好きなのにあまりしないの?」
現に、今日買ってきた花火は皆彼女が火を点けた。私は傍らに立って彼女がひとつずつ、外国の飴のように包まれた火薬と金属粉を色鮮やかな火の花に変化させるのを眺めていただけだ。
「打ち上げ花火が好きなの」
細い手が握った茎の先で咲く花の色が変わった。赤から、緑に。嬉しそうに瞳を眇めながら、そう言って彼女は笑う。
「火を点けられて、消える一瞬しか存在できない。花火として観る為には、そのもののかたちを失わなければならない。それってとても正しいと思わない?」
問いかけの形をとりながらも、その言葉は誰にも問うてなどいない。
「確かに観測することが出来るものなんて、屹度失われる瞬間だけよ。何もかも」
(『朽ちゆく花、落ちる花弁』)
|