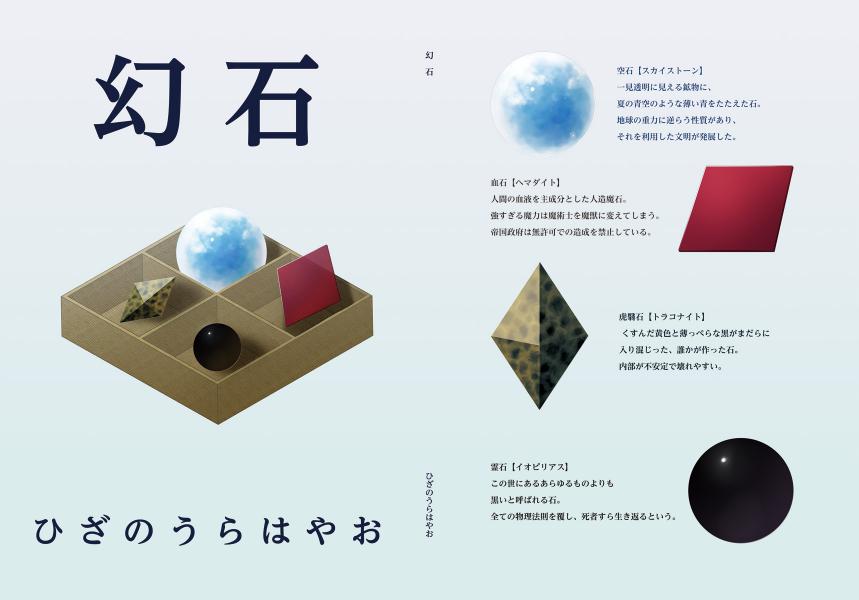|
「まだらな二人」(虎翳石:トラコナイト編)
「じゃあアレですか、最近滑り倒しなのは就職先見つけたからなんすか?」
清水の顔が一瞬こわばり、足にヒールの先が突き刺さる。でも俺は気にしなかった。
どうせこいつは芸人を辞める。あと何回も顔を合わせないうちにただの中年のおっさんになるのだ。もう知ったことではない。
だが、トンガリさんが俺に見せた表情は、先ほどまでとほぼ変わらず、柔和のままだった。
「――やっぱり小島には気づかれとったんか」
思い出した。中学生だったか、人生ゲームで運命の決算マスをすれすれのルーレットですり抜け、上がりが見えてる奴の顔とおんなじなんだ。だから、妙に焦らされるのだ。
「あんなあ、これいうのお前らだけや。事務所にも秘密にしてんねんけど――俺、結婚すんねん」
「えっ」
息を吸うのが精一杯の俺の横で、清水は鋭い声をあげた。
太くて無骨な指には似合わない、繊細な細いシルバーのリングを、トンガリさんはゆっくりと薬指にはめた。
「彼女とな、もう七年になんねん。劇場っちゅうんは先輩後輩ほとんど関係あらへんから、ギャラいうたらお前らとほとんど変わらん。――小島、これがどういう意味なんかお前ようわかるやろ?」
文字通り尖った顔で睨むように見つめるトンガリさんは、けれどいつものような凄みはもう消えていた。
「嫁さん食わすために、芸人辞めるんですか?」
俺の口調に、俺が一番ビビっていた。あまりにも、あまりにも平静を保てすぎた。
いつもの俺だったら、手に持っていたジョッキでトンガリさんの脳天をがっつり殴っていたような気がする。というか絶対そうしていただろう。いい加減にしろよ、とか、芸人なめやがって、とかふざけんじゃねえよみたいな感じの言葉を吐き捨てるように並べて。
だが不思議なことに、俺の中に一切そんな感情はなく、むしろ、どこか胸がすうっとするような安堵と、その脇に目をそらしたいほど醜悪な感情がともに芽生えていて、その場で頭を掻きむしりたくなった。清水はうつむいていて表情がよく見えない。
「おう。食えんと暮らせんからな」
一瞬、場が無言になる。
「それにな、もう潮時やってん」
朗らかな笑みを浮かべたトンガリさんは、もう芸人の顔をしていなかった。
|