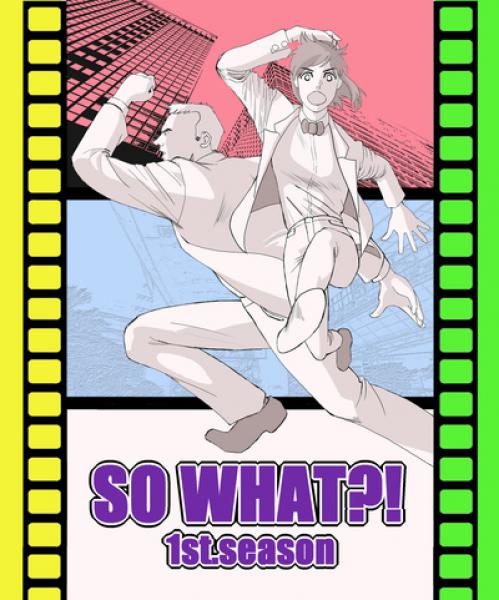|
駅から徒歩で十五分。
繁華街を抜け出せば、辺りはオフィスビルに囲われていた。味気なくも整然とした風景の中を、スーツ姿のサラリーマンにOLは行き交い、車がどこか気忙しげと走り抜けている。
片隅に看板は掛けられていた。
20世紀CINEMA
「うあ、……ほんとだ」
見上げて思わず百々(どど)未来(みらい)は、こぼす。すりガラスがはめ込まれた木製扉のその上の、レトロな飾り文字を読み上げ目を見開いていった。
ここに映画館があるらしいと知ったのは、駅中情報館のリーフレットからである。そこに上映スケジュールは掲載されると、裏面の地図に百々は首をかしげていた。何しろ全く覚えがない。就職活動時、何度か行き来したはずなのに、あんな場所に映画館なんてあったっけ、映画館といえば駅前のシネコンくらいしか思い出せずにいた。
だとして確かめ、わざわざ足を運んだのは、それら活動も実らぬまま卒業した今日この頃、持て余した時間が全てだ。こういう時ほど好奇心はうずくと、見つけた看板をこうして見上げていた。
扉にはめ込まれたすりガラスへ、顔を近づけてみる。ぼんやりとしか見通せなかったなら、ここまで来たのだ、えいや、で扉を押し開けた。広がる飴色の空間を前にして、「わぁ」と心の中で声をもらす。
薄暗いフロアの床は板張りだった。その両脇に奥へ向かってポスターは貼り出されている。突き当りにチケットカウンターはあり、そこに一人、係員は立っていた。他に人影は見当たらない。
百々は見知らぬタイトルの、見知らぬ俳優が四方へ視線を投げるポスターを、眺めて奥へと進んでみる。どのタイトルも観る者へ独自の世界を訴えていたなら、異世界を次から次へ旅してまわっているようだった。
どんなに慎重に歩いても鳴ってしまう靴音が、気にかかる。
やがて辿り着いたカウンターの横にイーゼルは、立てかけられていた。そこに今日の上映スケジュールは掲げられている。眺めて、カウンターの右手側、L字に折れて奥まったところにしつらえられた休憩ロビーへ視線を投げていた。
やっぱり、と引き戻して、財布を手に取る。
チケットカウンターは古いホテルの「それ」を思い起こさせる雰囲気をまとっていた。古いホテルの「それ」を彷彿とさせる係員から、次の上映チケットを買い求める。
平日の真っ昼間だからか、終了間際の作品だからか、たった三人のお客にと共に、スクリーンを見上げた。
二時間後、ほとほと泣かされフロアへ戻る。
|