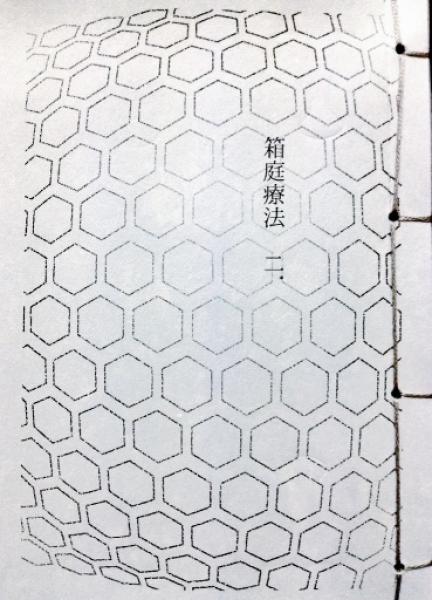
| ブース | 掌編1 ふじ文庫 |
| タイトル | 箱庭療法 二. |
| 著者 | 珠宮フジ子 |
| 価格 | 300円 |
| カテゴリ | 純文学 |
| ツイートする | Tweet |
| 紹介文 | |
|
誰かが居た日常を。誰かが居なくなった日常を。 それでも、世界は続いていくというそのことを。 とある疑似家族のちょっとずれた日常を綴った短篇集。 今回のテーマは「音楽」です。 132p・300円 【収録内容】 きらきら星 真夏のラプソディ・イン・ブルー (requiem aeternum) エッセイ「楽に寄す」 265 | |
僕の生家のグランドピアノの蓋には、たくさんの傷が付いている。割れたガラスを浴びたためについた、無数のひっかき傷。土地の名前を出しているのだから言うまでもないことかもしれないが、あの冬の、地震でついたものだ。
地震の前の日の夕方、僕は例のごとくピアノを弾いていた。その頃の――それは今もそうなのだが――僕にとって、ピアノを弾くことは日課以上の何かだった。夜半過ぎまでピアノを弾いた後、暖房はなく、電気ストーブだけで辛うじて暖められた部屋の床に丸まって眠ってしまうことも度々で、その日も丁度、そうだった。練習を終えた心地よい気だるさに任せて、僕は床にへたり込み、目を閉じて、眠ってしまっていた。そして、地響きで目を覚ました。地面が低く唸って、小刻みに、次いで大きく長く揺れた。
収まるどころか酷くなっていく揺れに、僕は頭を抱えて、ピアノの下から動けずにうずくまっていた。恐ろしく大きな、なにもかもがしっちゃかめっちゃかにひっくり返されていく音が聞こえた。食器棚が、冷蔵庫が、電子レンジと炊飯器の棚が、倒れて床に打ち付けられる音。食器が床に落ちて、粉々に砕け散る音。それから、すぐ近くでガラスの割れる音。そのときはとてもひとつひとつを認識することなど出来なくて、今から思い起こせばそれらが混じり合っていたとなんとか言えるけれども、地響きと一緒に通り過ぎていった大きな音に、僕は気付けば震えていた。
先ほどまでの喧騒が嘘のように静まりかえったのを聞きながら、僕は恐る恐るピアノの下から這い出した。真冬の早朝のことだったからまだ外は暗く、朝日の気配すら感じさせなかった。それでも、何故だろうか、床の上の細かなガラスの破片がきら、きらと光っているのはよく見えた。それを踏まないように床へ手をつくのが難しいほど、部屋の床には満遍なく、砕け散ったガラスが散らばっていた。
仕方がなく、僕はピアノの脚を持ちながらその場へ立ち上がったのだけど、思った通り、そこにあるはずの窓のガラスが、割れていた。砕け散っていた。冷たい風が直接、部屋の中を吹き抜けていた。潮のにおいは不思議と感じなかったように思う。海はあんなにも暗く、向こう側で波打っていたのに。風が冷たくて凍えそうだったので、僕は自分の肩を抱いていた。ふと視線をやったグランドピアノの蓋に、白いひっかき傷が、数え上げるにはあんまりにもたくさんついていた。